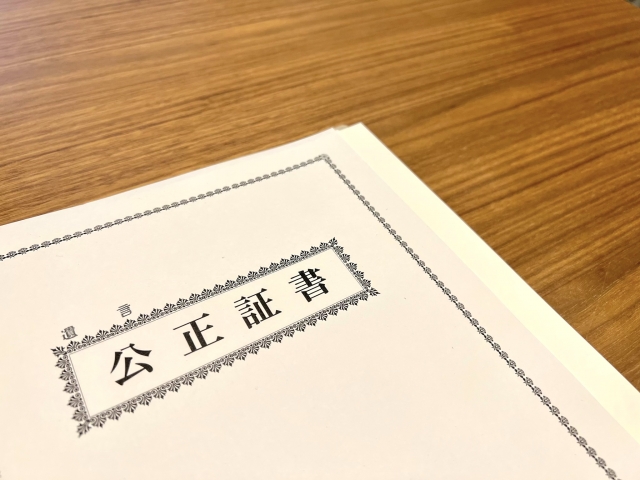
公正証書作成には、それなりに手続きに時間と手間がかかりそうですが、
実際はどんなことに注意しながら進めていったら良いのでしょう。
ここでは、公正証書作成をスムースに進めていくために、
おさえておくべきことについて解説します。
内容の整理と妥当性
公正証書を作成するための大前提として、
契約する当事者間で十分話し合いがされていて、
互いの合意があることが重要です。
公証役場は裁判所と違い、当事者間の紛争を解決してくれません。
話がすでにまとまっていて、内容も整理されていることが求められます。
具体的には、次の内容が決まっているか確認しましょう。
(1)当事者は誰なのか
(2)どのような財産、権利、法律行為についての公正証書なのか
(3)債務が履行されないときに強制執行できるのか
上記にような内容を確認した上で、
公証役場に一度相談をしてみます。相談は無料です。
その際、執務時間は9時から17時までが通常ですが、
12時から13時までの時間は昼休み(休憩)になるので、
その時間は避けるようにしましょう。
また、面談相談を希望する場合は事前に電話予約が必要です。
遠隔からの相談の際は電話やFAX、電子メールなどを利用して、
公正証書にする内容の妥当性をはじめ、必要書類などの確認をしておきます。
作成当日には公証役場に当事者が出向く必要がありますので、
日程調整も必要になります。
当日必要になる書類等
事前に公証役場に確認して書類等を準備しておきます。
当日必要になる書類等については、主に次のものがあります。
(1)本人確認書類
個人の場合・・本人を証明する書類等として、印鑑登録証明書と実印が一般的です。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの
身分証明書と認印も本人確認になります。
法人の場合・・登記事項証明書と代表者印とその印鑑登録証明書
(2)代理人に委任する場合の書類等
委任状と実印(法人の場合は代表者印)と、代理人の身分証明書
当事者がなんらかの事情で、公証役場へ出向くことができない場合は、
代理人に委任することができます。
代理人としては、家族、友人、弁護士などの専門家などです。
(3)不動産に関する書類
不動産の売買や相続などで、
公正証書の内容に不動産の記載が必要な場合は、
登記事項証明書(登記簿謄本)を準備し、
より正確な情報を明記することが求められます。
(4)遺言に必要な書類
財産の受け取る推定相続人又は受遺者を明確にするために、
相続人であれば、本人との続柄のわかる戸籍謄本を。
受遺者であれば、住民票を準備する必要があります。
作成当日の手続き
事前に日程調整を行い公正証書作成日を決定し、
当事者が揃って公証役場へ出向きます。
代理人に委任する場合でも同じように、
2人の間で結ぶ契約で双方ともに代理人を立てたなら、
双方の代理人が揃って公証役場へ出向くことが必要です。
また、遺言公正証書作成の場合は、証人2名が必要になります。
有料になりますが、相談すれば公証役場で手配することもできます。
当日は公証人が公正証書の内容を読み上げ、
その内容に間違いがないか、過不足ないかを確認し、
当事者(代理人)が署名・押印します。
これにより公正証書が完成し、
署名・押印によって公正証書の法的な効力が発生します。
公正証書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。