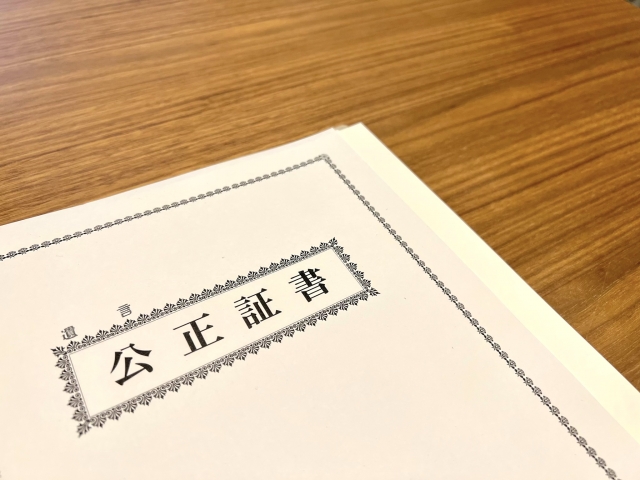
たとえば仕事の取引先と契約を結ぶことになり、
契約書を作成する必要があるとき、
これって公正証書にしたほうが良いのかな???
そんな疑問を今までに経験された方、
素晴らしいです。法的思考性を持ち、危機管理に優れた方です。
では公正証書にできるもの・でないものを解説します。
公正証書にできるもの
公正証書にしようとしたとき、
すべてのものが公正証書にできるわけではありません。
公正証書にできるものは、
契約書や遺言書などの権利義務に関係するものであることが必要です。
それは主に法律行為に関するものと、個人や法人の権利に関する事実証明になります。
(1)法律行為に関するもの・・・
権利義務の発生・変更・消滅の効果を発生させるための行為
・友人同士の金銭の貸し借り
・商品の売買契約
・不動産の賃貸借契約
・恋人同士の結婚の約束
・離婚に付随する財産分与や養育費の取り決め
・遺言書の作成ほか
(2)事実証明に関するもの・・・
個人や法人に認められる権利変動の原因となる事実を証明するための行為
・所有権
・抵当権
・賃借権
・著作権ほか
以上のことから、日常的に交わされる約束事のほとんどが、
公正証書の作成の対象になると考えられます。
当然に細かいことまで全てを公正証書にすることは、
現実的ではないと思われますので、その重要度だったり、
相手方との信頼の度合いや頻度などの問題により、優先順位も変わってきます。
公正証書にできないもの
日常的な約束もその対象となる公正証書ですが、
それでも公正証書にできないものもあります。
以下の内容については公正証書にできないものになります。
(1)公序良俗に反する内容のもの
・社会的な秩序や道徳に照らして、それに反する法律行為は無効となります。
(2)法令違反の内容のもの
・法律、政令、省令、条例などに照らして、
違反している内容のものは公正証書にできません。
(3)意思能力がない状態で作成したもの
・作成者に意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)が必要です。
(4)未成年者が作成したもの
上記のことから、たとえば遺言書を公正証書にしたい場合は、
遺言者に意思能力が必要とされているため、
作成者が認知症などの場合は、医師の診断等が必要になる場合があります。
公正証書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。