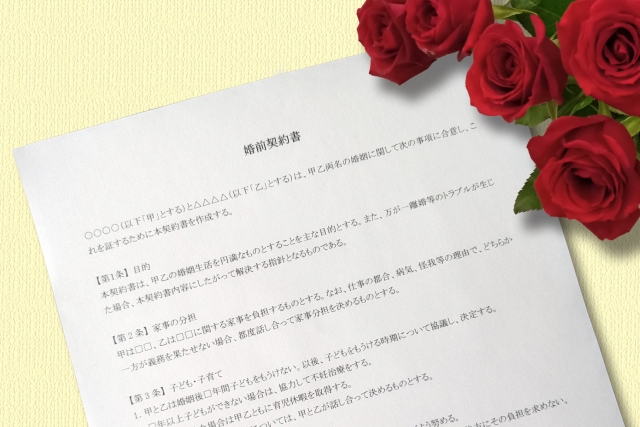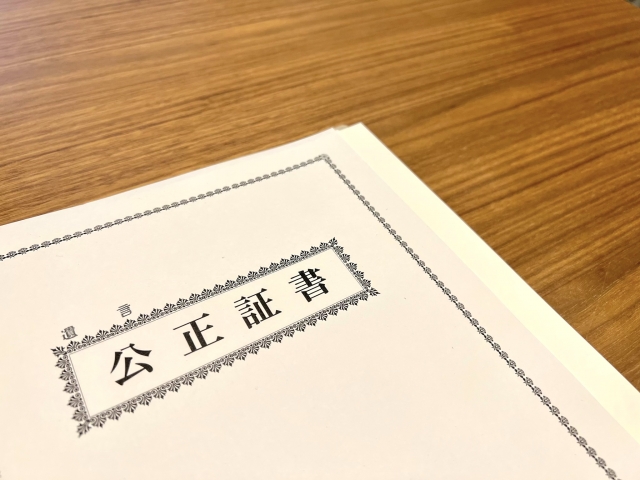
金銭の貸し借りによるトラブルが絶えません。
借りる側と貸す側との約束、これを金銭消費貸借契約と言います。
この契約を有効なものにして、トラブルを未然に防ぐにはどうしたら良いか?
一緒に考えていきましょう。
契約の成立要件
民法587条に消費貸借というものがあります。
「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」
という内容がそれにあたります。
つまり簡単に言うと、
お金貸してと言ってきた相手(借主)に、貸主がお金を渡すことによって成立する契約です。
1万円の金銭消費貸借なら、借主が貸主から1万円を受け取ることによって契約が成立します。
仮に、1万円を貸してほしいと言われ、
その場で、「いいよ」と返事をしただけでは契約は成立していません。
実際の金銭のやり取りがなければ、契約は成立したことにならない、
これが原則ですが、同じく民法587条の2では、この原則をひっくり返します。
「前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、
当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取ったものと種類、
品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」
つまり書面による合意がされていれば、実際の金銭のやり取りについては後でも、
契約自体は成立するということになります。
金銭の貸し借りによるトラブルを未然に防ぐため、書面にしておくことの重要性、
契約書の必要性について法律で明確に定められているといった感じです。
利息制限法
友人同士の貸し借りなら、利息を考えないということがありますが、
会社同士の貸し借りの場合には、利息の取り決めがなくても、
年3%の利率がつく場合がほとんどです。
ただし、消費者金融やクレジットカード会社などとの借り入れの場合、
当事者間の合意に優先するものとして利息制限法というものがあります。
これは債務者を保護するための法律で、以下のような制限が設けられています。
・元本10万円未満・・・年利20%
・元本10万円以上100万円未満・・・年利18%
・元本100万円以上・・・年利15%
たとえば、100万円の借入の場合に、20%の年利にしようとしても、
年利18%を超える部分は無効となります。
もちろんこのように違法な契約は、公正証書にすることができません。
遅延損害金
遅延損害金とは、返済期日を過ぎても支払いが無かった場合の、
債務不履行に対する損害賠償金ということになります。
利息制限法の定めによると、「利息の年利×1.46倍」という上限があり、
たとえば、借金が10万円以上100万円未満の場合であれば、
「18%×1.46=26.28%」が上限になります。
期限の利益喪失
期限の利益とは、返済日まで支払いを待ってもらえるという、
債務者にとってのメリットということになります。
返済期限までにきっちり返済されていれば、何も問題はありませんが、
これを守らない債務者の場合は、債権者としては困ってしまいます。
そのようなことを防ぐために、
「期限の利益の喪失」約款を書面に入れておくことをオススメします。
返済が滞った場合には、直ちに残金のすべてを返済してもらう約束になります。
公正証書
金銭消費貸借契約を公正証書にする場合は、
契約成立の要件や利息、遅延損害金、約定期日、期限の利益の喪失などを、
当事者間で取り決めておいて書面にします。
その他、公正証書には、
連帯保証人を立てたり、強制執行認諾約款も入れることが可能です。
詳しくはお近くの法律専門家にお尋ねいただくことをオススメします。
公正証書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。