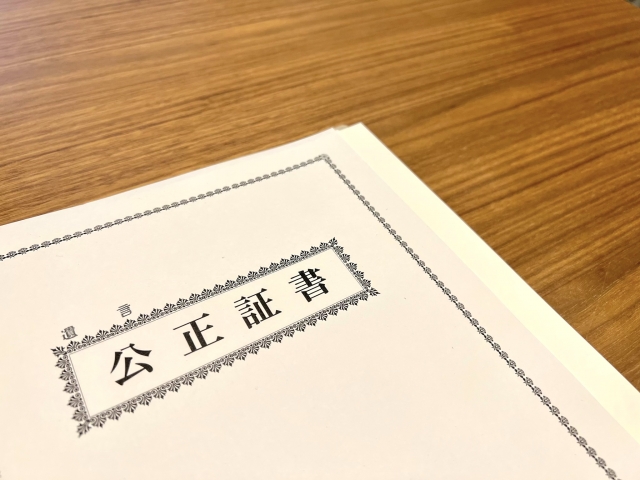
民法では、法定相続分が定められています。
相続の争いを避けるため、法律で法定相続割合が決められています。
しかし、この法律を破ることも法律で許されています。
なんか変な話ですが、、、
遺言書は法定相続分より優先する
法律を破ることも法律で許されている。。。
それが遺言書があるとき、又は相続人全員の合意があるときです。
相続人全員の合意は、場合によっては紛争に繋がる可能性も高いため、
遺言者の最終意思である、遺言書が果たす役割は大きいと思われます。
遺言書の法的効力には、主に次の3つがあります。
(1)遺産分割に関する事項
財産をだれにどれだけ渡すのか自由に決められます。
(2)身分に関する事項
認知することや廃除することができます。
(3)遺言執行に関する事項
相続発生後の遺言執行者を指定することができます。
安全安心は公正証書遺言
遺言書の種類には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」は、手軽に作れる半面、形式や遺言の内容などに不備があり、
無効になる可能性や、紛失・偽造の心配もあります。
それに比べて、「公正証書遺言」は、法律の専門家である公証人が作ること。
証人2名の立ち合いがあることなどから、無効になることはほぼなく、
安全安心な遺言書を作ることが出来ます。
公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言を作るにあたり、必要な書類を集めます。
推定相続人や受遺者に関する資料や、
財産目録はじめ不動産などに関する資料なども必要です。
本人確認のための資料や証人2名については住民票が必要になります。
では、もう少し詳しく見ていきましょう。
遺言者の本人確認資料
①運転免許証と認印
②パスポートと認印
③住民基本台帳カード(写真付き)と認印
④個人番号カードと認印
⑤印鑑登録証明書と実印
上記のうちいずれかを用意しますが、
原則は⑤印鑑登録証明書と実印を用意すると良いでしょう。
なお、印鑑登録証明書は3か月以内に発行されたものに限ります。
遺言内容を明確にする資料
推定相続人や受遺者の存在を明確にするために準備する資料
①戸籍謄本(遺言者と推定相続人の続柄がわかるもの)
②住民票(相続人以外に遺贈する場合)
相続財産を明確にするために準備する資料
①財産目録
②不動産がある場合は、登記事項証明書又は固定資産税評価証明書
③預貯金がある場合は、通帳のコピー
証人2名を決めておく
公正証書遺言作成には、
作成の当日に公証役場で立ち合いをする証人2名が必要となります。
証人になるための資格は特にありませんが、
未成年者や推定相続人は、証人にはなれません。
必要資料としては、証人なる方の住所・氏名・生年月日がわかるもの
たとえば運転免許証のコピーなどと印鑑(認印でも可)の持参が必要となります。
遺言執行者を決めておく
遺言内容の実現を円滑にするため、遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者には、推定相続人や受遺者も指定することもできます。
その場合は特に資料が必要になることはないですが、
第三者(弁護士などの専門家)を指定する場合は、
住所・氏名・生年月日がわかる資料が必要です。
例えば住民票や運転免許証のコピーなどになります。
まとめ
遺言書の目的は、相続が発生したときに、
遺言者の最終意思が遺言によって執行されることにあります。
そのための有効性を担保するために、
法律の専門家である公証人による遺言の形式や内容のチェックがされ、
証人立ち合いのもとで、遺言者の意思能力の確認や
手続きの真正さなどの事実が確認された公正証書遺言こそが有力と考えられます。
せっかく苦労して作っても、それが無効になってしまっては、
意味のないものになってしまいます。
遺言者の必要性を感じたら、
お近くの専門家に相談することをお勧めします。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。